こんにちは!薬剤師のぷちゃんです。私は薬剤師国家試験に浪人し、予備校に通わず合格しました。その経験をもとに、科目別の勉強方法を紹介します。
今回は化学の勉強方法についてです!
化学の勉強方法のポイント
化学は得意不得意が分かれる科目だと思います。
今回は、苦手という人向けに、化学の勉強方法のポイントを紹介します!

「現役で基礎はばっちり!得意!」という人は、過去問を解きまくる+足りない知識を都度追加していくやり方でいいと思います!
01|どの範囲から勉強するべきか
薬剤師国家試験における化学の出題範囲は大きく分けて3つあります。
- 化学物質の性質と反応(命名法、言葉の定義、基本的な化学反応、立体化学、有機化合物の基本骨格の構造と反応、官能基の性質と反応、化学構造の決定(~スペクトル読むやつ)、無機化合物)
- 生体分子・医薬品の化学による理解(生化学、医薬品の化学)
- 自然が生み出す薬物(生薬、漢方)
この3つのうち配点が高い+正答率が高いのは1です。
さらに1は、2を学習する際に前提ともなる基礎知識を含みます。
そのため、化学が苦手、基礎から不安という人は、まず1の基本的な化学物質の性質・反応から勉強を始めると苦手意識も解消しつつ得点アップも狙えるのではないでしょうか。
02|必須問題+正答率の高い問題+参考書で得点力アップ!
力を入れるべき範囲がわかったら、過去問と参考書を使って勉強をしていきます。
私は国家試験の勉強を過去問ベースで行っていましたが、化学に関しては参考書(青本)の解説や章末問題もかなり活用しました。
その理由は、先ほども述べた通り、基礎の部分が重要かつ頻出で得点に直接繋がりやすいからです。
過去問と参考書を使った勉強手順を紹介します↓
1.過去問を1問ずつ理解しながら解く(必須と正答率が60%以上の問題)
2.1問ごとに、題材にされている範囲の参考書の章(項)を確認する
3.確認した知識や、メモ書きは写真に撮るorメモ書きにして問題付近に挿入
4.その章の章末問題を解く
5.理解が浅いと思うところは問題集を使ってさらに演習
6.基礎知識がついてきたら正答率が低い問題にも挑戦→その問題の解法は理解しておく
私は最終的に過去問10年分を周回して国試に臨んだのですが、この方法で3-4年やり終えるころには段々と参考書に戻る回数も減り、理解度も高くなってると感じました。
(本当にめちゃくちゃ苦手、ちんぷんかんぷん、という人は5.6年分の必須問題だけ先にこの方法でやってみるといいかも)
とにかく、基礎の部分は参考書を使って丁寧に抜かりなく勉強していきましょう!
03|有機化学のポイント
☆とにかく手を動かす!
有機化学では、出発物質から正しい中間体や生成物を作らせる問題が多いです。そういう問題に対応する為にも、どこから矢印が出てどこにくっつくのかを理解して書けるように練習する事が重要です。
具体的な練習手順を紹介します。
1.過去問の解説や参考書を真似して矢印を書きながら反応式を完成させる
2.1で練習した反応式を何も見ないで書けるようにする
3.初めて見る問題に挑戦する。自分で考えながら矢印を書いてみて、正しい生成物にならなけ れば、どこが違ったのか確認して正しく書き直す。
このとき、代表的な求核剤(矢印の出発点)と求電子剤(矢印の着地点)をリストアップしておくと便利です。(先に暗記しておかなくても練習するうちに覚えられるものが多いです!)
よくある求核剤
- アニオン(-)
- ルイス塩基(孤立電子対:)
- カルバニオン(C–)
- アミン(:NR3)
- アルコール(R-OHのOの:)
- ハロゲン化物イオン
よくある求電子剤
- カチオン(+)
- ルイス酸
- 中性分子の陽性を帯びた部分(H2OのHなど)
- ハロゲン分子
この練習手順を繰り返していくうちに、矢印の出発点と着地点がわかるようになってきます。
また、参考書には、言葉だけで説明されている反応式や、途中経過が略されている反応があります。
私はなるべくそういうのも、自分でや印を書いて、スタート物質からゴールの物質を生み出せるように勉強していました。
こうすることで、暗記量が減り、理解で戦える部分が多くなるし、基本的な反応の復習をしながら応用に繋げることができました。
まずは基本的なSN1、SN2、E1、E2反応を手を動かしながら練習していきましょう!
☆暗記と理解を使い分ける
予備校生であれば、講師のここは暗記!ここは理解!というアドバイスを信じて勉強を進めていく良いと思います。
ただ、私のように宅浪で勉強しているとその指示がもらえないので自分で考える必要があります。
私も、最初から見極められたわけではなく、
1. まずは理解しようと試みる
2. ダメなら「暗記すべきもの」としてリストアップ
3. 周回するうちに「意外と理解でいけるやつだ」or「やっぱり暗記するしかないな」に分かれてくる
という感じでした。
最初から完璧に分けようとするのは難しいので、ある程度割り切って先の問題へ進むことが大事だと思います。
04|生化学のポイント
生化学の範囲はとにかく過去問を完璧にすることです。
既出の、アミノ酸、糖、脂質、ヌクレオチド、タンパク質、核酸については構造と名称を一致させることを理想に勉強しましょう。
特に、代表的な糖、核酸については生物の範囲でも頻出です。必ず覚えておこう!
05|生薬は捨てる?
結論、捨てちゃダメです。暗記だけで取れる部分が多い漢方、生薬の範囲を捨てるのはもったいないです。
特に、少ない暗記量で済む範囲は必ず抑えておきましょう!
生薬で優先して勉強すべき範囲
- 生薬の副作用
- 生薬の合成経路
- 代表的な生薬の構造、生物活性
まとめ
基礎は参考書や問題集を使って徹底的に!
生化学、医薬品の化学、生薬は既出問題を軸に勉強!
化学は苦手意識があると時間もかかるし精神的にもきついと思います。
でも、最初の基礎の部分と丁寧に向き合うことで、国家試験合格にグッと近づくはずです!
少しずつ、あきらめずに勉強を進めていってくださいね!
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)/
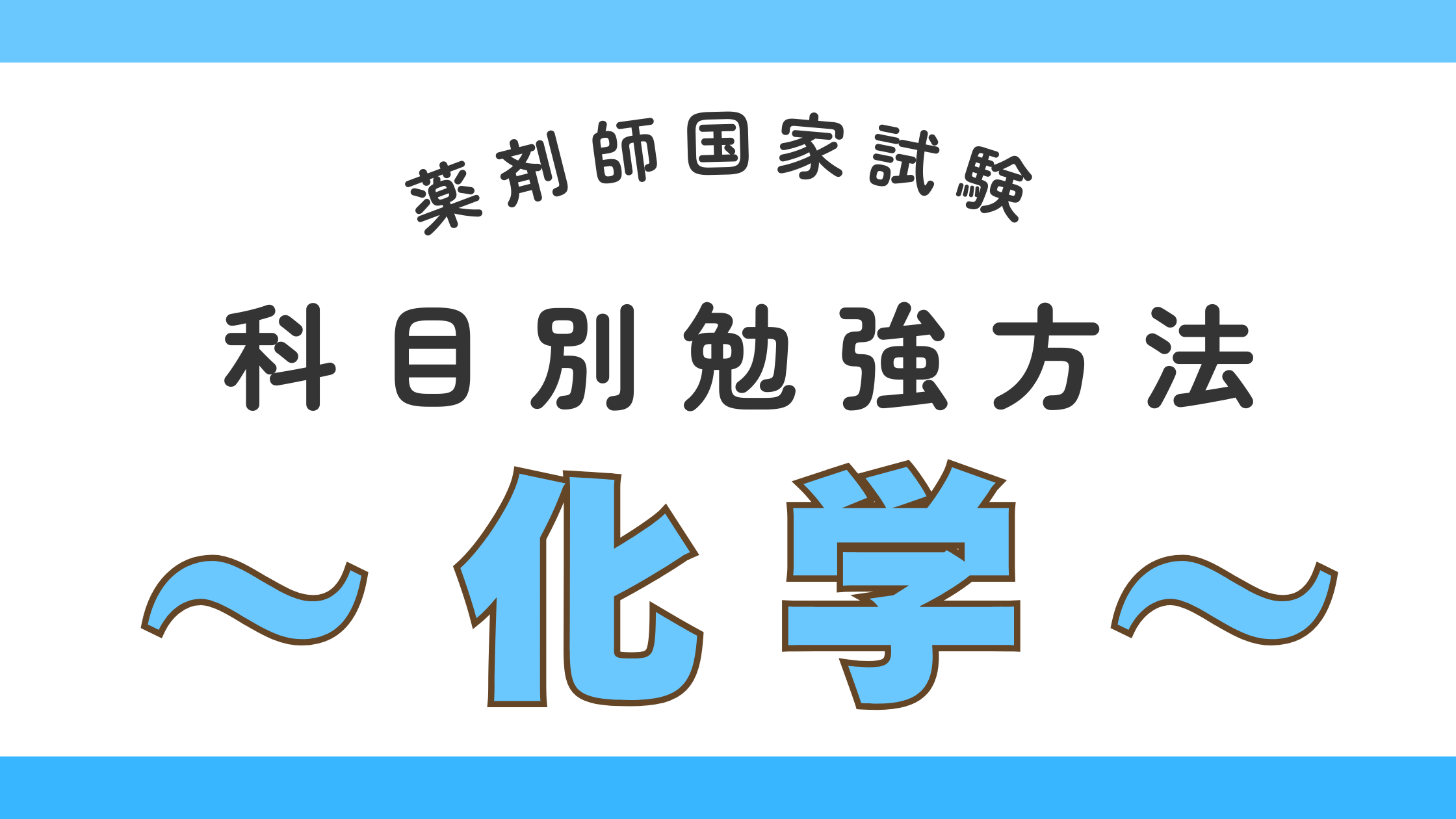


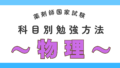
コメント