こんにちは。薬剤師のぷちゃんといいます!
今回は、新人薬剤師さんが直面する「患者さんとのコミュニケーション」に関する悩みについてのお話です。
服薬指導の時、最初から不機嫌だったり、無言だったりする患者さんの服薬指導について悩んでいる方は多いのではないでしょうか。実際私も、投薬を初めたばかりの時は、こういう患者さんにどう対応すればいいのかわからず、薬歴を書くのにも苦労していました。
しかし、そんな悩みを解消したのは、たった1つの方法でした。
それは「閉じた質問を1つ用意しておく」というシンプルなものです。
この記事では、私が実践している「閉じた質問を1つ用意しておく」具体的な方法や考え方について紹介します。
01|新人薬剤師がぶつかる壁「話してくれない患者さん」問題
国家試験を終えて、いざ意気込んで現場に立ったものの、思ったよりも患者さんが不愛想だったり、非協力的だったりして困惑した人もいると思います
私がまだ投薬台に立って数日目のある日の服薬指導でこんなことがありました
80代おばあちゃんの服薬指導。最初の挨拶をする間もなく「なんもないよ!早く!会計!」とキレ気味に言われてしまったのです。
正直に白状しますが、この時は本当に何も聞けず、言われるがままに会計してしまいました。そのため薬歴に書くことが何もなく、悩んだ挙句にSにはそのまま言われた言葉を、Aには「イライラしているのはホルモンの影響?(婦人科の薬飲んでたから)」とかそれっぽいけど何も根拠がない内容を書きました
今思えばいわゆるクソ薬歴なのです。が、当時はそれで精一杯でした。どうしていいかわからず、でも薬歴書をかない訳にもいかないし…と思ってそのようなことになってしまったのです
そして、そのことを先輩に相談しても「まぁ、そういう人もいるよ(笑)」と具体的な解決策はもらえませんでした
ただ、先輩の「そういう人もいるよ」という回答も見方によっては間違ったアドバイスではなくて「こういう人もいる」と割り切って日々の業務をこなしていれば、会話してくれない患者さんなんて、正直どうも思わなくなります。薬歴の内容も適当に書いておけば何とかなります。業務に支障は出ないのです
でもそれでいいのでしょうか。それでは薬剤師としての義務を”最低限”すら果たせていないのではないのでしょうか。
そんな葛藤から見出したひとつの解決策が冒頭でお伝えした「閉じた質問を1つ用意しておく」という工夫なのです
02|理想と現実のギャップ。理想通りにはいかない薬局薬剤師のリアル
ご存じの方も多いかと思いますが、厚生労働省が策定した「患者のための薬局ビジョン」というものがあります。
その中に~対物業務から対人業務へ~という表現があり、これが今、国が求める薬剤師の在り方です
とても素晴らしいと思います。
私はこれに大いに賛成であると同時に、現場のリアルな業務とのギャップを感じています
国家試験の出題傾向としても倫理観だったり、処方提案だったり対人業務に重点を置く流れがあります
繰り返しますが、ほんとに素晴らしいと思います。そうでありたいと思います。
ただ、それは未来を見据えた理想であって、「じゃあ明日から全薬剤師がそうなりましょう!」というのは、正直無理な話です
リアルな薬局の現場では、10種3剤の一包化90日分も、1剤PTPオンリー5日分も、同じ1枚と数えた40枚/人で設定された人員配置で、過誤やクレームが起こらないように神経をすり減らしながら働いている薬剤師がいっぱいいます
さらには、患者とうまくコミュニケーションをとって対人業務を頑張ろうと思っても、先ほどのように会話を始めてすらもらえないパターンもあるわけです
厚生労働省は、こういう現状を理想に近づけていこうという指針として、まず最終的な理想である「患者のための薬局ビジョン」を策定したのだと思います
だから、先に理想を勉強していると現場でガッカリしてしまう新人薬剤師の方もいらっしゃるのではないでしょうか
私もその一人です。こんな状況で患者一人一人に寄り添うって何言ってんだよ!って思います。
・・・でも、理想は素晴らしいなって思うんです
私は、このギャップを少しでも埋めるためにまずは、1回の服薬指導で”最低限”でもいいから対人業務だと言えることをするべきだと考えています
理想通りにはいかない。制度や会社が悪い。話してくれない患者さんが悪い。と何かのせいにして諦めてしまうよりも、何かひとつでも工夫をしてみる事で、この理想と現実のギャップを少しずつ埋めていけたらいいなと思います
この記事を書いたのも、そんな考え方もあるんだよ、と共有したかったのもあるかもしれません。
03|患者から情報を得る最も簡単な方法は「閉じた質問」をすること
では、実際に「服薬指導で患者から情報を経て薬歴を記載する」という最低限の対人業務をするにはどうしたらいいか、紹介します。
それは「閉じた質問」をすることです
【閉じた質問】
特徴:「はい」「いいえ」など回答の選択肢が限定される質問
目的:具体的な情報を短時間で確認するために使う
利点:短時間で知りたい情報が得られる
欠点:情報の幅が広がらない/多用すると単調な感じがして答える側が億劫になる
【開いた質問】
特徴:答えに制限がなく、自由に回答できる質問
目的:相手の考えや感じていること、背景情報等を詳しく引き出すために使う
利点:相手の意見や気持ちを深く理解できる
欠点:答えるのに時間がかかる。相手の能動性も必要になる。聞きたい情報を引き出せない場合がある
この2つの質問はどちらも服薬指導をする時に重要な要素です
理想は、この2つをうまく使い分けて患者さんの情報をより詳しく入手する事ですが、今回問題として挙げている「話してくれない患者」に最初にするべきは「閉じた質問」だけする事だと考えています
なぜこの考えに至ったのか説明します
まず、相手(患者)の言動の理由を考えてみます
「説明いらない。早く会計して」という高血圧治療中の患者がいたとします
(1)”なぜそんなことを言うのか”を考えてみます
→急ぎの用事がある・いつも飲んでる薬だから話す必要はない・個人情報だから薬剤師には何も教えたくない・薬剤師が嫌い・単純に会話が面倒くさいetc…
答えはこの患者本人にしかわかりませんが想像できるのはこの辺りです
(2)このように急いでるor話したくないと考えている人に「開いた質問」をしてみます
「最近体調はどうですか?」
返ってくるのは「別に」とか「いつもと同じ」とかです。最悪の場合は返事が来ません。
これでは何もわかりません。だって話したくないんですから。
開いた質問というのは相手に考えさせる質問です。答える側に労力をかけさせてしまいます。
そのため、話してくれない≒話したくない患者さんには不向きな質問だと言えます
(2)次は、閉じた質問をしてみます
「最近気温の変動が激しいですが、めまいや頭痛が起きることはありませんか?」
これなら「ある」or「ない」という事実のみ答えればいいので患者も答えやすいです
そして「ない」ならそのまま薬歴に書けばいいし、「ある」なら副作用の確認の会話を始めるきっかけになります。
このように、「閉じた質問」をすることで話してくれない患者から、1つだけでも情報を得ることができます。
だから私は、服薬指導に行く前に「閉じた質問を1つ用意しおく」ように習慣づけています。
試してみると意外と答えてくれます。
というか事実を答えるだけの質問をされると、多くの人は反射的に「イエス」「ノー」を答えてしまうんですよね
私のように、「話してくれない患者」に対してどうしたらいいか悩んでいる人はこの「閉じた質問を1つ用意しておく」方法を真似してみてください
04|服薬指導は完璧じゃなくてもいい
ここまでの内容を読んで「薬剤師、こんなんでいいのか?」と不安に思う方もいらっしゃると思います
逆に「うんうん、こんなもんよね」と共感してくださる方もいると思います
私が服薬指導で悩んでいる新人薬剤師さんに伝えたいのは「服薬指導は完璧じゃなくてもいい」ということです
服薬指導は患者さんとの会話です。この会話をいかに円滑に、うまく進めるかも薬剤師の技術だと言えますが、最初から完璧にうまくできる人なんていません。
それに会話というのは一人だけ頑張っても絶対うまくいきません。
理想は、患者からの信頼を得て、説明は全部聞いてもらって、悩みは全部相談してもらって、それに対して正しい指導や医師への提案を行うことかもしれません。
それが、薬剤師として患者の役に立ったと実感できる部分でもあると思います
でもそれって毎回、誰が相手でもできますか?
理想はあくまで理想です。大切なことはこの理想に向かってまず何をするか、です。
最初は何も話してくれなかった患者さんも閉じた質問を毎回ひとつしておくことで頭の片隅に自分が飲んでるお薬や治療中の病気に関する情報が残ってることがあります。
それをふとした時に思い出して、次の受診で医師に相談してくれるかもしれません
それがきっかけで処方が変わるかもしれません
そうなったときは、言葉にしなくても「あの時の薬剤師の質問が役に立ったな」と思ってくれるかもしれません。
そしたら結果的には、直接相談してもらって医師に提案したのと変わりないです
かもしれない、ばかりだけど薬剤師の仕事ってそういうものなんです。
目に見える大きな活躍なんて年に1回あるかないかです
でも一回一回の調剤、服薬指導が患者のマイナスをゼロに近づけるために必要な行為です
1回の服薬指導で全てを完璧にできなくても、その1回で要点を絞って1つでも患者さんと情報交換ができればいいと私は考えています。
05|「閉じた質問を1つ用意しておく」時の注意点と具体的例
1つ質問すればいいなら簡単そう!と思った方は要注意です。
この方法は、薬剤師が楽するための方法ではなくて、あくまで患者さんから情報を得て安全な薬物治療をサポートするための方法です
1つの質問だとしても薬剤師はそこのところしっかり理解しておく必要があります。
注意点を3つ具体例を挙げながら紹介します
1.処方監査は完璧に
服薬指導は完璧じゃなくていいとお伝えしましたが、それは調剤・処方監査が完璧である前提での話です
当たり前のことですが、用法用量や服薬期間に問題がないか・調剤に間違いがないかは投薬前に自分でも確認しておきましょう
2.いちばん聞くべき質問を選ぶ
1つしか質問しないので、その1つの質問は慎重に選ぶ必要があります
判断材料は前回の薬歴、服用中の薬の情報などです
(1)前回の薬歴から、「前回は何を質問してどんな答えが来たのか」を確認し、内容によって違う質問をするのか、関連する質問をするのか選ぶ
【具体例】
- 前回薬歴S「めまいなどの副作用はないです」→今回は残薬など服薬コンプライアンスについて確認しよう
- 前回薬歴S「少し頭痛があるがたまになので大丈夫」→頭痛の悪化がないか、頻度が増えてないか確認しよう
- 前回来局時に処方変更があった場合→その薬について質問する
(2)服用中の薬について季節ごと(気温・花粉など)の注意や、副作用のリスクになりうる要因がないかなど細かい所にも焦点を当てると質問の幅が広がる
【具体例】
- SGLT2阻害剤服用中→気温が低いですが、副作用予防のために水分補給はしっかりできていますか
- 降圧剤服用中→暖かくなってきましたが、いつもより血圧が低すぎる日はありませんか
- 抗凝固薬×高齢者→歯医者さんで治療を受ける予定はありませんか
3.質問の答えに対する対応も考えておく
ただでさえ話たくないと思ってるのに、「ただ聞いただけ」で終わる質問をされたらその患者さんはさらに何も話してくれなくなります。
質問をしてきたから返事をしたのにあたふたされたり、「そうですか」で終わったりすると信頼はガタ落ちです。
質問をするならばそれに対する返事を必ず考えておく必要があります
【具体例】
- 副作用所見有無を確認→副作用の疑いがあるならどうするのか
- 飲み忘れの有無を質問→飲み忘れた時の対応法を説明できるか、残薬があるならどう対応するのか
- 大丈夫です→これからも○○には注意してくださいね(質問の意図を伝える)
- なんでそんなこと聞くの?→自分が質問している内容の意義を理解しているか
このように「閉じた質問を1つ用意しておく」とは、毎回お決まりの質問をしておけばいいということではなくて、その質のこだわっていちばん聞くべき1つを選んでおくということです。
まとめ
今回は、新人薬剤師さんが直面する「話してくれない患者さん」問題の解決策として「閉じた質問を1つ用意しておく」ことを紹介しました
薬剤師として実際に患者さんと接すると、いろんな悩みに直面し、自分の力不足を実感したり、薬剤師の仕事のやりがいについて疑問を持ったりすることがたくさんあると思います
患者さんが何も話してくれないと「必要とされてないんだな」と感じてしまうこともあります
それでも、大切なのは、目の前の一人の患者に対し今の自分ができる最大限のことをしようと考えて実行していくことです
薬剤師の仕事は患者さんあってこそです
だから患者さんの態度や状況によって、業務内容や自分の感情が変化します
だからすごくストレスもたまるし大変ですよね
でもそんなときに患者さんのせいにするのではなくて、「なぜこの患者さんはこうなんだろう」とか、「この患者さんに自分ができることは何だろう」とか考えるのが薬剤師には必要なことだと思います
私も悩みや不安(不満)が尽きない毎日ですが、なんとかやっていこうと思っています
私の投稿が少しでも新人薬剤師さんのお役に立てばうれしいです
最後まで読んでいただきありがとうございました!

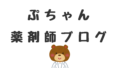
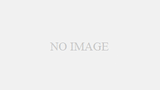
コメント